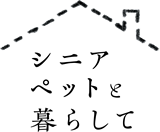「わかったよ、おかあさん。」
平成28年3月11日。
悪性リンパ腫を患い、2年3ケ月の闘病の末、私の犬、チベタンスパニエルのLeoは天国に旅立った。抗がん剤など、辛い治療を、雄々しく耐え、2回もの寛解を迎えることができた。
覚悟していたつもりだった。けれど、まだ温かい亡骸と対面した時の、底なしの絶望感は今でも薄れることはない。
Leoは賢い犬だった。
「ドア閉めて。」と頼めば、立ち上がって、勢いよく両前脚をドアに預け、バタン!と戸を閉める。料理中など、手が離せない時に、何とも頼りになる相棒だ。
時に功名心が過ぎ、ドアを開け放しておきたい真夏にも、先回りして閉めてしまうのは、玉に傷だったが...
「ベッド、お片付けして。」と言えば、お気に入りのペットクッションを咥えて、ケージの前までずるずると引きずって行き、入口の前で一旦置くと、先に自分がぴょんと中に入る。今度は中からちょいちょいと前脚を出して、クッションをケージの中に引きいれて、お片付け完了。この「ちょいちょい」が実に絶妙で、何度見ても笑ってしまった。

Leoは、他にも沢山の芸をすぐにマスターした。真ん丸の大きな瞳を輝かせ、「どうです?おかあさん、僕って、すごいでしょ!?」と言わんばかりの得意満面の表情で私を見上げてくる。
表情がとびきり豊かで、気持ちがすべて顔に表れる。それを私がアフレコしてみせると、本当にLeoがしゃべったようで、息子達は大笑いしたり、本気で憤慨したり、愉快なこと極まりなかった。
Leoは、優しい犬だった。
穏やかで幸せな日々は、突然終わりを告げ、暗雲垂れこめる苦難の時がやってきた。家族は一人去り、二人去り、やがて家には私とLeoだけが残された。胸を掻きむしるような思いで、私が一人泣いていると、家のどこにいようと、Leoは気配で察知して、飛んでくる。私の膝の上に上ると、零れ落ちる涙を、いちいち優しく舐めて拭ってくれるのだった。ふさふさした、立派なしっぽを、ゆっくりと振りながら、静かな微笑んだような表情を浮かべていた。「おかあさん、僕がいるじゃない。ね、ずっと一緒にいるでしょ。」そう言っているようだった。こんな小さな生き物が、精一杯私を慰めようとしてくれる。有難くて、嬉しくて、私はこの尊い命が私の元に遣わされた奇跡に感謝せずにはいられなかった。
彼が息を引き取ることになるその日、わたしは深夜までの仕事があった。幾多の治療に耐えてきた彼もさすがに疲れた様子で横たわっている。もう、限界だろう...私も認めない訳にはいかなかった。
「れおちゃん、今まで、本当に本当に有難うね。おかあさんを守る為に、今まで頑張ってくれたんだよね?ごめんね、辛い思いさせちゃって。れおちゃんのお蔭ておかあさん元気になったから、もう、おかあさんのために頑張らなくっていいんだよ。もう大丈夫。」

そう言うと、Leoは寝たきりになった身体で唯一気持ちを伝える手段として、耳をピクピクと10回動かした。
すぐ様私は、その意味を理解した。
「わかったよ、おかあさん」その10文字を渾身の力を振り絞って伝えると、私の出かけるのを見計らって息を引き取ったのだった。
いつの日か、私があの世に逝った時には、真っ先に駆け寄ってくるに違いない。
「それまで待っててね。もうひと頑張りするからね。」